Susanne Mentzer (スザンヌ メンツァー)は1957年米国生まれのメゾソプラノ歌手。
モーツァルト作品を得意とし、多少響きに独特なヴィブラートがあるものの、
決して太くはないが芯のある美しい中音域を聴かせる現在の米国人歌手にはまずいないタイプである。
余計なことをしないでモーツァルトを歌う。ということが如何に難しいことか!
メンツァーはとても簡単に歌っているように見えるが、
大抵の歌手ができないことで、演劇的になり過ぎてしまったり、
逆に軽やかな音楽に相応しくない声で歌ったり、
変にテンポを揺らしてモーツァルトの音楽を台無しにしてしまったり、
だからと言って単調な歌でもいけない。
2018年のメトでドラベッラを歌ったマルフィはこんな感じだ
セレーナ マルフィ
明らかに喉声のイタリア人メゾがメトでドラベッラをやっているのが現状。
全く音楽に推進力がなく、
メンツァーの小気味よいテンポの中で表情が目まぐるしく変わる様子を見事に表現した演奏とは対照的である。
このメンツァーの表現は、
もしかしたらパヴァロッティのマスタークラスの影響もあるのかもしれない。
ここでの指摘をそのまま実演でやっているのが以下の映像
https://www.youtube.com/watch?v=H0wvpTfZ9sg
テンポ通りよりやや先取りして有声子音を響かせ、ソプラノのような高く軽い響きで歌う。
それでも持っている声がメゾソプラノなので、ソプラノのようでもソプラノではない響きになっている。
後この人の良いところは、子音が硬くないところ。
角の立たない子音で見事に言葉をレガートで繋げている。
現在の米国を代表するメゾ、ディドナートと比較すればその違いは明白
ジョイス ディドナート
ディドナートは少なくとも現在の米国人メゾではトップクラスの実力者。
決して悪くはないが、音域によって響きがかわってしまう。
単純に声質だけ比べればディドナートの方が癖がないのだが、
響きという面では違う。
例えば
Sento un affetto pien di desir,
ch’ora è diletto, ch’ora è martir.
Gelo e poi sento l’alma avvampar,
e in un momento torno a gelar
メンツァー(9:00~)
ディドナート(0:54~)
まず、「ch’ora è martir」
微妙にディドナートは”o”母音が鼻声になり、「martir」で完全に響きが崩れる
一方メンツァーは全く響きの質が変わらない。
更に顕著になるのが
「Gelo e poi sento l’alma avvampar」
ここは表現的にも音域的にも、胸声でドスの効いた声を出す人が結構いるのだが、
仮にも声変わりしてない少年がそんな声出すかよ!という話で、個人的にはそういう歌い方はNGだと思っている。
ディドナートは別に胸声に落としているとまではいかないが、
「vampar」だけ明らかに響きが変わってしまい、
「avvampar」という単語には聴こえない。
この部分のメンツァーの歌唱は本当に素晴らしいと思う。
バリトン トマス アレン
本来ソプラノが歌ツェルリーナ役だが全く違和感がない。
メンツァーの発音でちょっと問題があるとすれば”i”母音でやや響きが低い(音程的にもやや低く聴こえる)。
ただ、この曲。
軽いソプラノが歌うと、ソプラノの声が浮いてしまって全く美しくハモらないことがあって、
それはなぜかと言えば、テッシトゥーラが低い曲なので、中低音で響きが落ちる歌手が歌うと絶対はまらない。
重唱の定番曲ではあるが、意外と美しくハマった演奏は少ない。
コレは名演奏だと思う。
やっぱりモーツァルトのスーブレット役は軽いソプラノが歌うべきものではない。
ソプラノに近い響きのメゾ、あるいはそれに近い響きをもったソプラノが歌ってこそ、
本当にモーツァルトの音楽らしい調和と、生きた言葉が生まれる。
それにしてもメンツァーのイタリア語の子音の扱いは素晴らしい。
ハッキリ聴こえる中でも硬さが全くなくてレガートで繋がる。
こういう演奏がもっと評価され、日本でもスタンダードになるように、
これからも記事を書いていこうと思う。

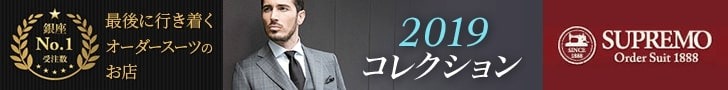
コメントする